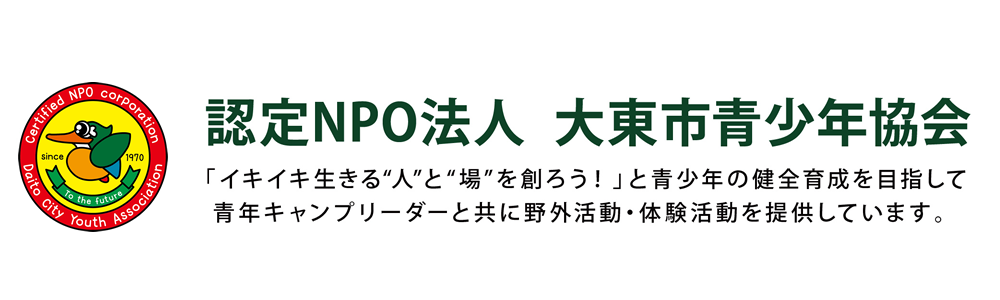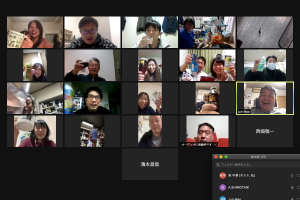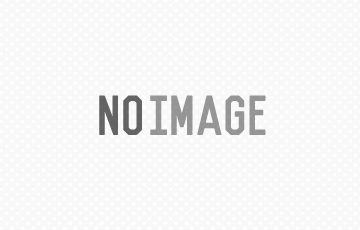キャンピィだいとうにある田んぼで江戸時代や明治時代に実際に使用していた貴重な民具を使って、稲作体験を行う「民具×米作り体験」。
第4回目「草取り」を6月19日(日)に、第5回目「わら細工&草取り」を7月10日(日)に、第6回目「草木染め&草取り」を8月11日(木・祝)に行いました。
「米」という字を分解すると「八十八」という字になりますが、これは収穫までに88回もの手間がかかるということが語源で、収穫までにいかに除草を行うかで、収穫数が変わってきます。
6月の草取りでは、回転式除草機と呼ばれる明治時代に発明された除草機を30cm間隔で植えた稲と稲の間を通し、除草していきます。
7月と8月は稲も育ち切っているので、全て手抜きで雑草を抜いていきました。
3日程ともとても暑く、塩分、水分補給と休憩を挟みつつ、除草作業を終了しました。
6月は田んぼの畔道に枝豆を植えました。畔豆と呼ばれ、水田に必要な栄養を送り込み、化学肥料がなくとも田んぼの状態が良くなるらしいです。
7月は昨年収穫した稲わらを使ってわらぼうきや馬の人形を作りました。
8月は玉ねぎの皮、びわの葉、たで藍の葉を使って草木染め、藍染めを行いました。
昔ながらの農法や自然の工作など先人の知恵がびっしり詰まっており、非常に勉強になります。
職員 のっち